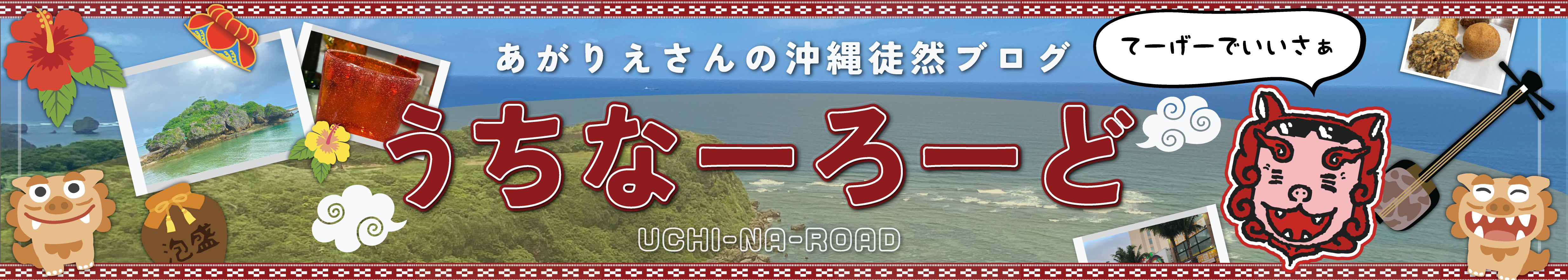去年は沖縄に行ったから今年はどこに行こう」なんて、言っていたはずなのに
「北海道がいい」とか「ネズミの国」がいいとか言ってたはずなのにー
気がついたら那覇空港にいてしまうような沖縄好きの戯言です。
No.60 憧れのしまくぅとば
沖縄県人には理解できない”憧れ”が、僕にはあります。それは、音を聞くだけで心を癒し、イントネーションに心を和ませ、稀に意味が分かると至上の喜びに満たされる・・・”うちなーぐち”です。テレビでガレッジセールのゴリさんの話すうちなーぐちが理解できていたのなら、司会者の10秒手前で笑えるのにと何度思ったことでしょう。
テロップで流れると「わかるかも?」と思う事もあるのですが、耳から入る音だけでは全く理解できません。よくYouTubeを見ていると『聞き流すだけで英語が話せる』なんて広告が流れますし、動画でもその類のものは多いように思います。僕は「英語の授業さえ無ければ、行きたい高校、行きたい大学に進めたのに」と妄想するくらい英語が苦手ですから、いくら『おばあさんでも』って言われても、それで話せないなら、「俺って80代のおばあちゃんより理解力が低いんだ」って落ち込むじゃないですか。でも、『聞き流すだけで、誰でもうちなーぐちが話せるようになる』CDがあったら買うと思います。「そんなのできる訳ない」と90%思っていても買うような気がします。
内地で暮らす沖縄大好き人間を僕は「うちないちゃー」と呼んでますが、少なくとも内地の沖縄好きにとって最大のハードルは「うちなーぐち」だと思います。
ところが、沖縄県では若者のうちなーぐち離れが加速していて、オジーやオバーが話す言葉を理解できない人も増えているとか。そこで、なんと腰を上げたのは”沖縄県”でした。9月18日を語呂合わせでくぅ(9)と(10)ば(8)の日と定めたり、「しまくぅとば普及推進計画」を制定したりと、言葉の文化は沖縄文化の基層であり、言語を大切にすることは県民のアイデンティティを守ることであると考えたわけでしょう。
で、もう疑問に思う頃でしょう。「うちなーぐち」と「しまくぅとば」って同じなの?ってね。
先に僕の誤った認識をお伝えしておきます。「うちなーぐちの古い言い方がしまくぅとば(島言葉)で、沖縄弁と言うニュアンスだと”うちなーぐち”で琉球言語と言うニュアンスだと”しまくぅとば”になる」と、勝手にカッコつけて思っていましたが完全に間違っていました。ほとんどと言うか正解の部分がありません。自分勝手に想像したシナリオがソレっぽくて自分が自分に騙されていました、こんな知ったかぶりを人に言わなくて良かったと思います。
実は、「しまくぅとば」という言い方が新しいのです。見ての通り”しまくぅとば”は”島言葉”ですよね、では「島」って沖縄本島なの?石垣島?宮古島?奄美大島は?波照間島、久米島、鳩間島、竹富島(ごめんなさい、すべては書き切れません。)と、考える訳です。でも、内地の僕から考えるに全部沖縄県です(奄美大島は違いますけど。)から、”島”は特定の島ではなくて琉球文化圏の島だと思っています。ところが、少し沖縄のブログなんかを書いていると沖縄の言葉は本島と離島では全然言葉が違う事を知りました。それどころか、同じ沖縄本島でも地域によっては言葉が通じないとか。(これは沖ツラでひーなーも言っていました。)交通や地形や色々と理由はあるのでしょうが、地域の工芸品を王府に上納していた時代に技術の流出を防ぐために他の地域との交流を自ら断っていたとも言われます。
そこで、少し調べると僕の大好きな阿波根あずささんが動画で解説してくれていました。”しまくぅとば”の”しま”は”島”以外に”故郷という意味があって、しまくぅとばとは「生まれ故郷の言葉」という意味になります。つまり、”しまくぅとば”は琉球文化圏全体の言葉をさしていて、石垣島生まれの人も宮古島生まれの人も本島北部の人の言葉も含んだ呼び方になるのです。
一方で、”うちなーぐち”ですが、狭い意味では那覇や浦添と言った本島中南部で使われている言葉を指すそうで、宮古島や石垣島には”うちなーぐち”という言葉は無いそうです。それに代わる「みゃーくふつ」「やいまむに」というのが「地域の言葉」という意味だそうです。
沖縄情報の発信源として多く使われた”うちなーぐち”が広義で沖縄県の言葉=沖縄弁として認識されているようです。最近では「うちなーやまとぐち」という言い方もあって、標準語を取り入れた分かりやすい”うちなーぐち”だそうです。
では、僕が覚えたい”しまくぅとば”は何なのでしょうか?実は、「沖縄の人が言っている事がわかるの!」と友人に言われると満足するレベルで良いんです。
いつも見ている”おきなわチャンネル”で「ゆさたるぐとぅうにげーさびら」って言われても字幕がないと意味が分からないのが、嫌なんです。

頑張って、イントネーションは近づけても、「ふらー」とか「にふぇー」と「あぎじゃびよい」とか方言の意味はわからない。大体、「沖縄」が「うちなー」になるのだって、沖縄方言で「そう言う」なんて思っていたのです、が、違いました。この変換にはきちんと文法があったのです。
まず、母音の「a,i,u,e,o」の「e」と「o」が「i」と「u」に変わるというのは前から知っていました。雨(AME)が(AMI)=「あみ」になるみたいな感じですね、カラオケで「この」を「くぬ」と歌って知ったかぶってます。
また、ki , ky → ci とか ri → i とか教えられても、「はい?」って顔になるし、ai , ae → ee (母音重ねは長音になるらしい)ですよとか、awa → aa も、その変形ですとか聞かされても、「英語の文法も嫌いやった」と思い出すだけです。
ただ、これを「沖縄」に当てはめてみましょう。沖縄=おきなわ=OKINAWAですね。まず先頭の「O」が「U」で、「KI」が「CI」でしたね。これで、「おき」が「うち」に変換されました。次に最後の「AWA」ですが、これは長音の「AA」でしたね。続けると「OKINAWA」が「UCINA」に変換されました。ローマ字にすると変化しなかったのは「N」だけですね。
どうでしょう?「しまくぅとば」は憧れですが、「英語の文法」と同じで教科書で理解するのは僕には無理でした。でも、アメリカに住めば英語は話せるようになると言いますし、沖縄に移住できればしまくぅとばもペラペラになるに違いありません。
ちなみに、那覇市の文化振興課によると
「しまくとぅば」を直訳すると「島の言葉」で、その意味は、村落、島、故郷を表します。「しまくとぅば」は概ね、6つに分類され、奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語に分かれています。「うちなーぐち」は沖縄語のことで、しまくとぅばの1つですが、「うちなーぐち」の中にも首里言葉、糸満言葉などがあり、これらも「しまくとぅば」に含まれます。
と記載されていました。